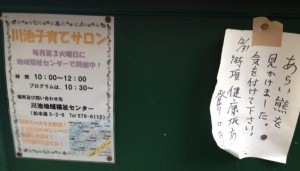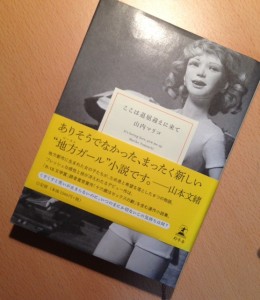神戸市の直近の人口(推計人口)は、2014年6月現在、153万8454人です。
東京23区を除けば、横浜、大阪、名古屋、札幌に次いで、全国で5番目の大都市です。
そして、神戸に次いで人口が多いのは、福岡市です。
残念なことですが、神戸の人口は、ごく近い将来、福岡市に抜かれることは確実です。
2014年6月 神戸市 153万8454人 福岡市 151万5995人 その差は、22459人
2013年6月 神戸市 154万867人 福岡市 150万2354人 その差は、38513人
2012年6月 神戸市 154万3951人 福岡市 148万9142人 その差は、54809人
ここのところ、2年続けて、16000人を超える人口差の縮小が続いていますので、早ければ2015年秋、遅くても2016年春には、神戸市と福岡市との人口が逆転する可能性が高いと考えられます。
福岡市は、一貫して人口が増加してきました。かつて京都市の人口は福岡市より多かったのですが、2011年6月に福岡市が上回りました。
我が国の人口が減少している中で福岡市の人口が増え続けているのは、福岡市が九州の中枢都市であり、福岡県を含むほかの地域から人口を吸収し続けているからです。同じ事情は、札幌にも当てはまります。
人口は都市の活力のバロメーターですから、福岡の人口が神戸を上回ることになるのは、神戸を愛する市民のみなさんにとっては受け入れにくいことかも知れません。
しかし、長年続いてきた傾向を考えれば、これは、神戸市民が向き合わなければならない事実です。
その上で、神戸が、居住都市としても「選ばれる街」の地位をどう回復させていくのか、しっかりと議論を行い、政策展開を図っていかなければなりません。