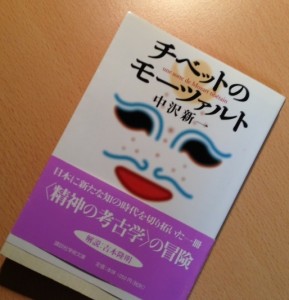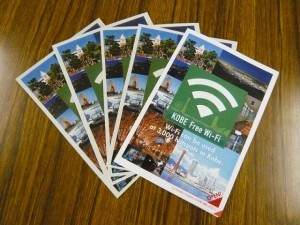7月30日の毎日新聞夕刊に、「幻の防災計画、震災4日前に答申 耐震化など提唱」という見出しの記事が掲載されていました。
「阪神大震災が起きた1995年1月17日のわずか4日前に、神戸市が建物の耐震化促進や防災ボランティアの育成など、先駆的な防災対策を盛り込んだ基本計画をまとめていたことが分かった」
というものです。
記事によれば、この基本計画案には、神戸には「多くの活断層が存在し地震発生の可能性も否定できない」と明記され、「社会の防災力が低下してきている」と警鐘を鳴らしていました。その上で、「防災対策として▽都市の基盤や建物、公共施設などの耐震強化▽幼少期から防災教育を推進し、防災意識を高める「防災博物館」の整備▽防災行政の一元化−−などを列挙。防災ボランティア活動の推進と評価する仕組みも挙げた」とあります。
震災前、審議会委員として防災対策を取りまとめた室崎益輝神戸大名誉教授の「当時としては画期的な内容だった」というコメントも記されていました。
震災前、神戸市では、第4次神戸市基本計画の策定作業中でした。市民参加のもとで原案が作成され、この原案に対する総合基本計画審議会の答申が平成7年1月13日になされています。
記事にあります「幻の防災計画」とは、この「第4次神戸市基本計画原案に対する答申」のことです。
震災直後、神戸市行政に対してはさまざまな批判がなされましたが、そのひとつが、神戸市は株式会社神戸市として開発行政ばかりを重視し、防災への取り組みを怠った、というものでした。
この記事は、当時の神戸市政が、地震の発生に対する問題意識を持ち、必要な対応を考えていたことを明らかにしてくれています。
提言された対応をとる間もなく、あの日を迎えることになったのですが、その内容は、平成7年10月に策定された第4次神戸市基本計画に盛り込まれ、今日までその着実な実施が図られてきています。