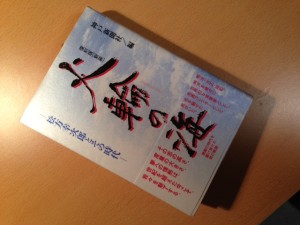何とか基本計画、何々事業計画、++計画、○○プラン、**ビジョン・・・・・役所には、どうしてこんなに計画のたぐいが多いのでしょう。
主要な行政分野に計画ができれば、さらにその中の各分野の計画がつくられ、さらに、その下の計画が求められ、際限なく枝分かれしていくような印象さえ受けます。
さらに、計画をいったんつくれば、その進捗状況を把握し、外部の視点を含めた評価が行われ、その評価をもとに、計画を改定するサイクルが理想の姿だと言われます。
こうして、膨大な計画の作成・改訂・点検の作業が、役所のあちこちで行われています。
これらの大半は、職員のデスクワークです。机上の作業です。
もちろん、市政全般にわたり、また、それぞれの行政分野で、きちんと将来を見据え、計画的に仕事を進めていくことは大切です。
しかし、市役所の中の多くの組織において、年がら年中、このような、いわば「作文行政」がまかり通っているとしたら、それが本当に市民のための仕事になっているのかどうかは、大いに疑問です。
無駄な作文はやめ、むしろ求められる課題に対して、迅速に行動し、目に見える成果に結び付けていくようにすることが求められているのではないでしょうか。
幸い、改革の芽は生まれています。
神戸市の「神戸2015ビジョン」については、これまで、市長・副市長、局室区長がメンバーになっているビジョン推進本部を開き、改定作業を行っていました。
企画調整局では、この本部を廃止し、作業を大幅に簡素化して、最小限の改訂を行うことにしました。
また、各区計画については、改訂そのものを行わないことにしました。
このような「作文行政」からの脱却が、市役所の中に広がっていくようにしていきたいと思います。
無意味な「作文行政」に耽っている組織・人員を削減する一方、市民サービスに汗を流し、あるいは、新しい課題に果敢に挑戦している組織・人員を拡充していくことが求められます。