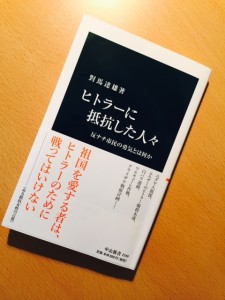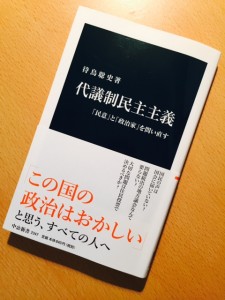
本書の中で、対となって頻繁に登場する用語が、自由主義と民主主義です。
自由主義とは、多様な考え方や利害関心を持つ人々の代表者が相互に競争し、過剰な権力行使を抑制しあうことを重視します。
これに対し、民主主義は、有権者の意思(民意)が政策決定に反映されることをまずもって追求しようとします。
自由主義のために存在していた議会が民主主義と結びつき、20世紀に入って代議制民主主義が成立しました。
しかし、両者が理想とする政策決定のあり方は大きく異なっており、原理的な緊張関係が存在していると、筆者は考えます。
この相克を出発点として、歴史的な考察、現代政治の課題の分析、制度的な考察を通じて、代議制民主主義の改革の方向性が語られます。
最近の論調では、代議制民主主義に限界を感じ、熟議型民主主義、国民投票や住民投票、ネットでの意思決定など代議制民主主義以外の方策により政治不信を乗り越えようとする方向性が目立ちますが、筆者は、代議制民主主義になお希望を託します。
代議制民主主義は、「しなやかかでしたたかである」からです。
つまり「偶然に合流したはずの自由主義的要素と民主主義的要素がせめぎ合い、それぞれが過剰に意味を持ちすぎることを防ぐ」からです。
この二つの要素をどのようにバランスさせるのかについての考察も、具体的になされており、結論に説得力を与えています。
しかしそれでもなお、米国の政治のゆきづまりはかなり深刻であることを、本書を読んで改めて感じました。
政治権力が分割されている統治構造の下で、極端な民意の「分極化」が進めば、政治は漂流する危険を孕みます。
代議制民主主義は、つねに試練にさらされ、その克服への葛藤を刻み続ける運命を課されていると感じました。