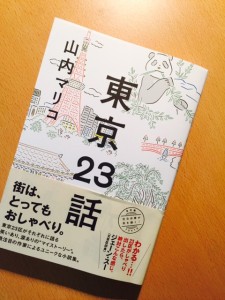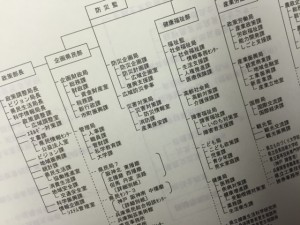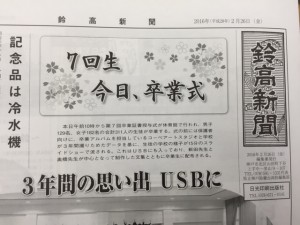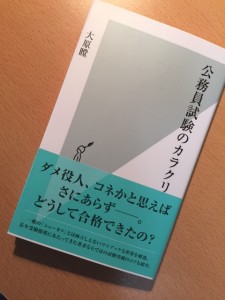昨日、市会に提出した平成28年度予算と関連議案などの議決をいただきました。
それらの中に、旧二葉小学校の「神戸市立地域人材支援センター」(神戸市長田区二葉町)の名称を「ふたば学舎」に変更する条例改正案があります。

この施設には何度もお邪魔しましたが、地域のみなさんからは、
「施設ができるとき、昔からなじんだ『ふたば』という文字を入れてほしいと何度も市役所にお願いしました」
「しかし、全市的な施設なので特定の地域の名前を入れるわけにはいかない、との理由でかないませんでした」
というお話をお伺いしてきました。
その都度、「それはおかしいですね」と申し上げてきたのが影響したのかもしれませんが、昨年暮れ、自治会、婦人会、学校関係者などから構成される旧二葉小学校活用委員会から「ふたば学び舎」に変更してほしいという要望をいただきました。
この要望を踏まえ、今回条例改正案を提出することにした理由のひとつは、「地域人材支援センター」と呼ぶ方がほとんどおられないということでした。
たいていの方は、「昔の二葉小」とか単に「ふたば」などと呼んでおられました。
呼んでもらえないような名前は、施設の名称としてそもそも不適当です。
また、全市的施設だから特定の地域の名称を使ってはいけない、というのもおかしな話です。
そんなことを言うなら、王子動物園や北野工房も不適当な名称なのでしょうか。
訳のわからぬ屁理屈で地域の声を封殺するような態度は、許されません。
それに地域性の尊重は、地方自治の大事な要素です。