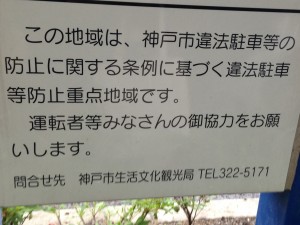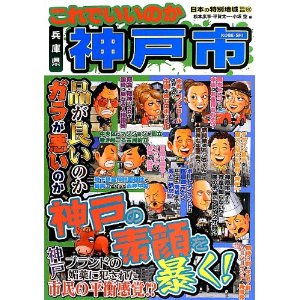北区淡河町の「道の駅 淡河」が、開業10周年を迎え、きょう記念事業が行われました。
「道の駅」の制度ができたのは、1993年4月のこと。一般道路でも、高速道路のサービスエリアのような休憩施設を、という声が高まったことが背景でした。
神戸では、2003年4月に、「道の駅 淡河」が、政令指定都市で初めて誕生しました。
北区淡河町は、六甲山系の北側に位置し、町の中央を淡河川が流れる、自然が豊かな田園地帯です。
小部小学校時代の恩師は、ここ淡河から、神姫バス、神戸電鉄を乗り継ぎ、鈴蘭台の小部小学校へ通っておられました。
私は、昨年11月に神戸に帰ってきましたが、ほどなく、恩師がその年の1月に亡くなられていたことを知りました。
下の写真は、昨年12月、恩師の遺影に帰郷を報告するため、恩師宅をおたずねしたときに撮影した、淡河の風景です。
淡河は、米どころで、代表的な酒米、山田錦の産地として知られますが、新鉄砲ユリ、チューリップなどの花の栽培のほか、そば、野菜づくりにも力を入れています。
「道の駅 淡河」では、豊富な種類の淡河産野菜・果物のほか、新鉄砲ゆりやチューリップ、北神みそといった地元特産品を揃えています。
また「レストランそば処 淡竹」では、淡河十割そばを楽しむことができます。JAや地元女性会が中心となって運営が行われており、多くのお客で賑わっています。
「道の駅 淡河」10周年記念事業では、野外でも、たくさんの産品が販売され、地域のみなさんによるアトラクションも行われました。
平成24年度の来場者数は約20万人、売り上げは2億円を誇ります。
「道の駅 淡河」、そして、淡河町のすばらしさを、広くもっと知っていただき、ひとりでも多くの方に訪れていただきたいと願い、会場を後にしました。