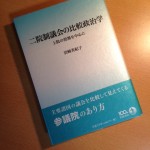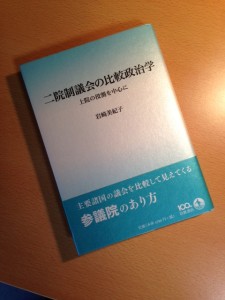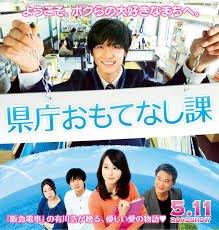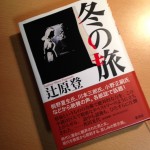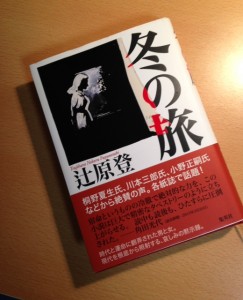ミシガン州のデトロイト市が破産したという記事が、大きくニュースなどで取り上げられています。
7月18日、デトロイト市は、連邦破産法の適用を申請しました。自治体が破産を申請するには、州知事の承認が必要で、ミシガン州のシュナイダー知事は、申請を承認しました。
我が国では、自治体が破産する制度は設けられていませんが、アメリカでは、自治体も、民間企業と同様に、破産することがあります。
連邦破産法は、基本的には、民間企業の破産の要件、手続き、効果などを規定した法律ですが、第9章で、自治体の破産について規定しています。
破産手続きは、民間企業、自治体とも、裁判所の関与の下に進められ、債権債務の整理が進められます。
第9 章では、地方自治体の場合の特例が規定されており、破産した地方公共団体が財政再建に取り組んでいる間は、債権者の債権回収から一定の 保護が受けられます。
また、民間企業の場合は、最終的に清算されることがあるわけですが、自治体の場合は、清算はありませんし、債権者に収益が分配されることもありません。
破産手続きは、債務調整計画が策定され、破産裁判所の監督の下に進められます。
我が国の場合は、自治体の債権について債権放棄は行われませんが、連邦破産法に基づく債務調整計画には、債権放棄を盛り込むことができます。
しかし、その一方で、歳出についても大胆に見直しが行われ、職員の解雇や一定の行政サービスの停止が行われるのが通常です。
職員の給与も大幅に引き下げられ、年金についても、給付削減が行われます。
デトロイト市も、これから、イバラの道を歩むことになるでしょう。