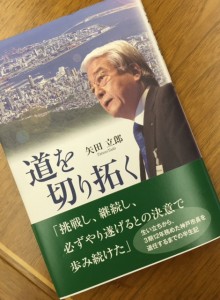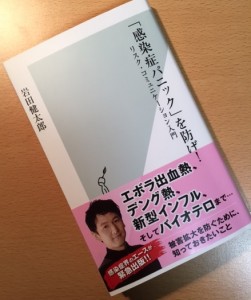少し前のことになりますが、1月14日に「歌会始の儀」が皇居で行われました。
今年のお題は、「本」。
美智子皇后は、次のように読まれました。
来(こ)し方(かた)に本とふ文(ふみ)の林ありてその下陰に幾度(いくど)いこひし
本を文の林に喩えられ、幾度となく本で憩われた想いが表現されています。
美智子皇后が少女時代から本を友として成長されたことは、知られています。
想い起こすのは、1998年、NHK教育テレビで放映されたご講演です。インドで開催された会議に寄せられたビデオによる講演で、英語で行われました。
タイトルは、「子供の本を通しての平和-子供時代の読書の思い出-」。
美智子皇后が、少女時代に読まれ、心に刻まれた読書の記憶を語られたものでした。
子供時代の本の感想といった域を超えた高度な内容で、優しく、しみじみとした、高貴な語り口とともに、鮮明に覚えています。
美智子皇后は、自らの来し方と重ね合わせ、多感な少年・少女時代における読書の大切さを、一貫して訴えてこられたのではないでしょうか。
子供たちが読書の習慣を身につける上で、保護者の役割は大きいと思います。幼い子供に、童話などを読んで聴かせてあげることは、素晴らしいことだと思います。
また、学校でも、子供たちが本に親しむことができるような環境を整えることが必要です。読書に親しむことで豊かな感性を育むとともに、本で調べる習慣を身につけ、自発的な学習意欲に結びつけて行ければと思います。
子供たちに読書の習慣を身につけてもらう上で、 学校図書館における学校司書の役割は重要です。
神戸市では、平成26年度に初めて小学校20校、中学校10校にモデル的に学校司書を配置しました。
来年度は、引き続き、予算措置を講じ、最終的には全ての小学校・中学校に配置していきたいと考えています。