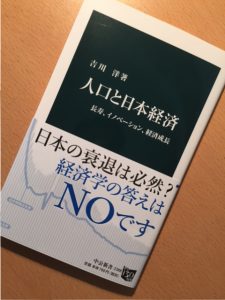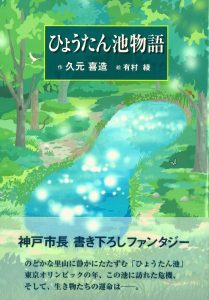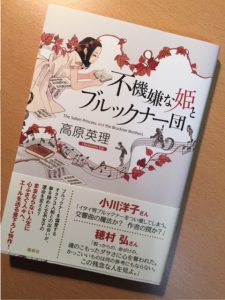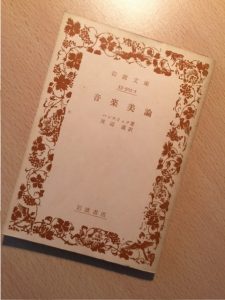インフルエンザが流行るころになると、中二の時の自転車事故を想い起こします。
学級閉鎖になり、これ幸いと、同級生とふたりでサイクリングに出かけました。
鈴蘭台から二軒茶屋に出て有馬街道に入り、箕谷から山田中学の前を通り、われわれはペダルを漕ぎづつけました。
「餓鬼の喉」を越え、山田の田園風景を眺めながら颯爽と進みます。
途中で道は下り坂になり、右にカーブして山田川にかかる橋を渡るはずでした。
ところが・・・まるで分解写真を見ているようでした。
先を走っていた私は、カーブを曲がりきれず、橋の欄干に激突してしまったのです。
気が付いたら、自宅の布団の中でした。
ずいぶん長い間、気を失っていたのでしょう。
何が起こったのか、理解できませんでした。
しばらくして激しい吐き気に襲われ、私は何回も洗面器に吐き続けました。
往診に来られた先生が、脊髄から水を抜きました。
めちゃくちゃ痛かったです。
歳月が流れ、4年前、神戸に戻ってしばらくして、四十年ぶりに同級生と再会しました。
新開地の居酒屋で酒を酌み交わし、自転車事故のことを尋ねました。
彼は鮮明に覚えていて、あのときのことを詳しく説明してくれました。
橋の欄干に激突した私の体は、2メートルか3メートル跳ね上がって宙に舞い、道路の上にたたきつけられたのだそうです。
「川に落ちたら死んどったで」
確かにそうでした。
自転車は、自らに対しても、他者に対しても、凶器になり得ます。
くれぐれも運転には気を付けてください。