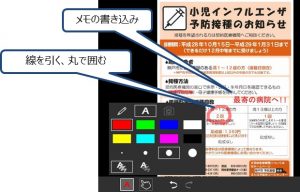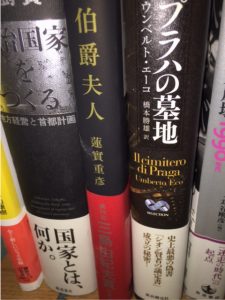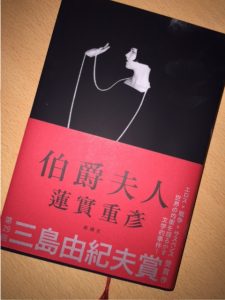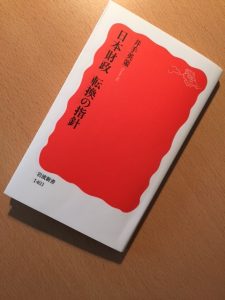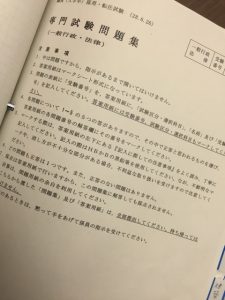米国大統領選挙から1週間が過ぎました。
あの日、11月9日(水)午前9時半から、庁内で「英語による政策討議」が開かれました。

冒頭、私は次のように挨拶しました。
拙い英語ですが。
Good Morning!
Are you interested in the result of yesterday’s election?
Of course, I am.
The result of the election will affect the relationship between Japan and the United States.
But we are working for Kobe City.
So, we have to make Kobe great again! (笑)
このとき、私は、トランプ氏が勝利するだろうと感じていました。
想い起こしていたのは、3年前の自分の選挙です。
すべてのマスコミの事前予想は、私の「リード」「優勢」を報じていました。
しかし私はそうは思いませんでした。
私は、主要政党、そして幅広い分野の団体から推薦、支持を受けていました。
そのような雰囲気の中で、私以外の候補者を支持している方が正面から聞かれれば、そのことを正面切って言いにくいのではないか。
それに、マスコミの事前調査は、一定の補正をかけるとは言え、固定電話にかけるやり方です。
報道には疑問を感じていましたが、案の定、薄氷の勝利でした。
今回の大統領選挙では、主要マスコミはクリントン氏を支持し、トランプ氏に厳しい批判を浴びせていました。
そんな空気の中で、トランプ支持と言いにくい雰囲気は間違いなくあるだろう、その数は相当多いのではないかと想像していました。
あの日の夕方、トランプ氏の当選を、密かな満足感を感じながら聞きました。
私は、自分の選挙は弱いのですが、選挙ウォッチャーとしては優秀なのです(笑)。
もちろん、こんな自己満足に浸っていてはいけません。
仕事をしなければ!