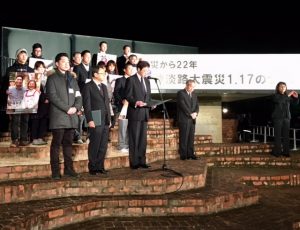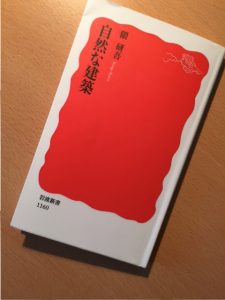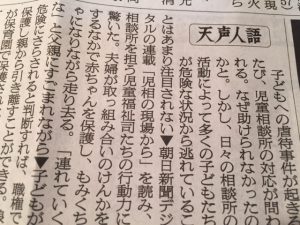昨日行われた安倍総理大臣の施政方針演説では、水素社会について、次のように触れられています。
「水素エネルギーは、エネルギー安全保障と温暖化対策の切り札です。これまでの規制改革により、ここ日本で、未来の水素社会がいよいよ幕を開けます。三月、東京で、世界で初めて、大容量の燃料電池を備えたバスが運行を始めます。来年春には、全国で百か所の水素ステーションが整備され、神戸で水素発電による世界初の電力供給が行われます。
二〇二〇年には、現在の四十倍、四万台規模で燃料電池自動車の普及を目指します。世界初の液化水素船による大量水素輸送にも挑戦します。生産から輸送、消費まで、世界に先駆け、国際的な水素サプライチェーンを構築します。その目標の下に、各省庁にまたがる様々な規制を全て洗い出し、改革を進めます」
神戸で進めている水素発電の実証実験、昨年 1月27日のブログ でも取り上げた水素サプライチェーンの構築について触れていただき、名誉なことと感じています。
水素ステーションについても、昨年11月7日の臨時記者会見 で発表しましたが、今年の3月に兵庫区七宮町で神戸で初めて営業をスタートさせます。
神戸から本格的な水素社会を始動させていく意気込みで取り組みます。