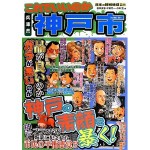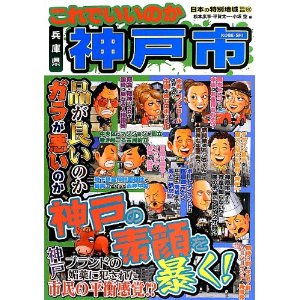我が国の統治構造は、国においては議院内閣制が、地方自治体においてはすべて大統領制(二元代表制)が採られています。いわば、常識に属することがらかもしれませんが、主要国においてこのような組み合わせをとっている国は、我が国以外にはありません。
地方自治体において大統領制(二元代表制)が採られているのは、地方自治体の知事や市町村長が、住民の直接公選により選出されることが、憲法上の要請だからです。
憲法は、「地方公共団体の長、その議会の議員および法律で定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」(憲法93条2項)と定めます。
終戦直後の日本政府内部では、とくに都道府県知事については、間接選挙を支持する声が圧倒的でしたが、GHQの強い意向により、直接公選とされました。GHQは、我が国の民主化のためには、とりわけ都道府県知事の直接公選が不可避だと考えていました。
導入の経緯は、他律的でしたが、地方自治体における大統領制(二元代表制)は、当事者の感覚も含めて我が国において定着し、安定的に運用されているように見えます。
しかしながら、国地方の統治構造全体を見たときに、国が議院内閣制で、地方が大統領制という組み合わせが、中長期的に見たときに本当に安定的かどうかは、疑問が残ります。
議院内閣制は、国会の信任の下に存続し、与党が安定した勢力を保ち、内閣を支える立場に立つときは強い政治的リーダーシップを発揮することができます。
一方、地方自治体の長は、直接住民から選挙で選出された点において民主的正統性を得ており、民主的正統性の根拠は議会の信任にあるわけではありません。
まったく異なる代表制原理で成り立っている国と地方自治体が、今後、本当に安定した国地方関係を築いていけるのか、また、両者に意見の相違が生じたときにどう解決していくのか ― 現時点では、問題は顕在化していませんが、内政上、重要な論点であることは間違いありません。