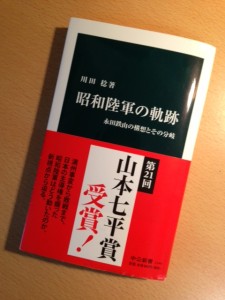北区鈴蘭台にある、神戸市立小部小学校の同窓会が開かれ、出席させていただきました。
小部小学校は、明治7年(1874年)に創立された、由緒ある小学校です。来年、創立140周年を迎えます。
藤田操校長先生から、小部小学校の歴史や近況、子どもたちの作文が紹介されました。
興味深く、心がこもった、簡潔な報告でした。女性の校長は、藤田操先生が創立以来はじめてだそうです。
同窓会のあと、懇談会が開かれ、私から、在学中の思い出や神戸市の課題、神戸への想いについて、お話しさせていただきました。

私は、ちょうどオリンピックの年、昭和39年(1964年)に、川池小学校から小部小学校に転校し、昭和41年(1966年)に卒業しました。
小部小学校に在学したのは、1年半足らずでしたが、当時の6年2組の子どもは、ほぼ全員が、箕谷の山田中学校に進んだので、私にとっては、小部小学校、山田中学校の4年半は、一体となった、懐かしい思い出になっています。
当時は、まだ、木造の校舎、木造の音楽室があったこと、あちこちに池があり、鮒を釣ったり、泳いだりしたことなどをお話ししました。
「川池小学校と小部小学校では、校風は違いましたか?」と尋ねられましたので、「全然違いました」と答えました。
確かに、同じ兵庫区(当時は、まだ北区はできていませんでした。)でも、こんなに違うのかと思うほど、学校の雰囲気は違っていました。
人口がどんどん増え、プレハブ校舎を建てて対応しなければならず、神戸電鉄は満員で、積み残しができるほど混雑していた時代は、もう半世紀も昔のことになりました。
地域社会のありようが大きく変わった今、鈴蘭台など北区に何が求められているのかなどについても、簡単にお話しさせていただきました。
半世紀前を思い出しながら、母校をあとにしました。