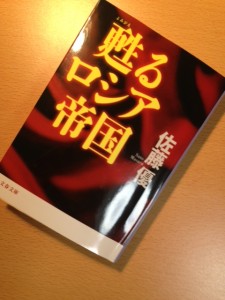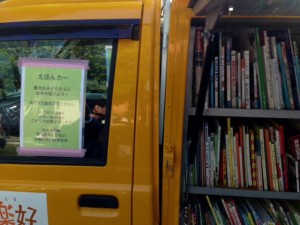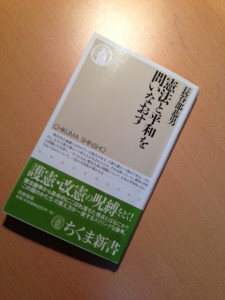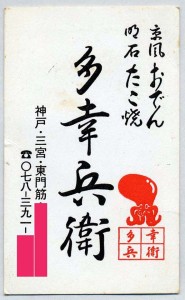さわやかな5月の日々が過ぎていきます。
この季節に、ふと耳に聞こえてくる歌が、R.シュトラウスの『万霊節(Allerseelen)』です。
香り高い金木犀を テーブルに置き
最後の赤いアスターをもって こちらへおいで
そして再び愛について語ろう
かつて5月にそうしたように
花々が咲き誇る5月の、愛の歌のように聞こえます。追憶の気配を伴いながら。
手を出して そっとにぎらせておくれ
誰かに見られてもかまわないから
君のやさしい眼差しを わずかでも見せておくれ
かつて5月にそうしたように
そこで突然、場面は、「万霊節」の日に転換します。
ここで、恋人が亡くなり、その追憶の歌であることがわかります。
魂の高揚とあたりの静けさが、墓地を支配します。
すべての墓には花が咲き誇り 香りが漂っている
きょうは 一年に一日だけの 死者が解き放たれる日
おいで僕の胸に そしてまた抱かせておくれ
かつて5月にそうしたように
歳をとるということは、自分が生きているのに、その一方で、肉親や友人、大切な人を失っていく過程なのかもしれません。
それはとてもつらいことです。とりわけ、その人のことを深く愛し、その人が本当にかけがえのない存在であった方にとっては。
それでも、失った大切な人は、残された者の中に生き続けることができます。
高校生の時に読んだ、ロマン・ロラン『ジャン・クリストフ』の中の一節
「死者は生者とともに生き、生者とともに死ぬ」
という一節を想い起こします。