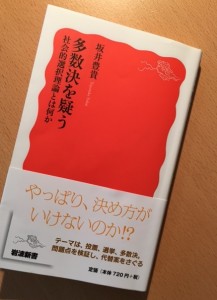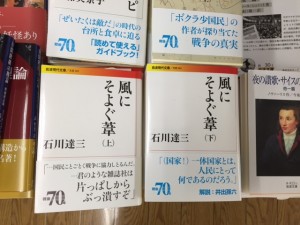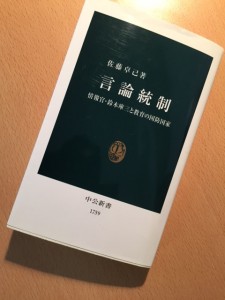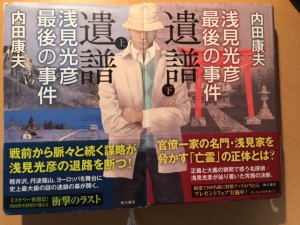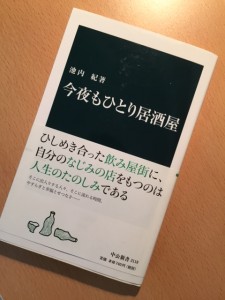きょうは、午前中の公務の後、午後から北区山田町の農地を歩き、稲の生育状況と耕作放棄地を含めた水利の模様を見学しました。

山田町の農村は、稲刈りの季節を迎えています。
白いサギが田圃の上を舞っていました。

残念ながら耕作放棄地が見られます。

そんな中にあって、この田圃は、長く耕作放棄地だったのですが、農業委員や地元のみなさんの努力で、若い新規就農者が新たな挑戦を始めています。
すでに草が刈られ、綺麗に整地されていました。

ここには、すぐに使える用水の水栓もあります。
もともとこの辺りの耕作放棄地では、用水はいつでも使える状況で、新規就農がいつでも可能とのことでした。

用水は、山中を源流とする川から取られており、池の水は、よほどの渇水のときしか使われないようです。
このためか、池と上流の川とはつながっておらず、水が循環しないため、濁っています。
水質が良くないと米の味にも影響があると言われますが、現状の水利で足りるため、池の水質改善の必要性は高くないようです。

田圃の畔近くで、ヤマカガシが這っているのを見かけたので、一瞬たじろぎましたが、残念ながら、死んでいました。
ヤマカガシを見たのは、久しぶりです。(8月2日のブログ)

呑吐ダム湖畔から、山中に入って10分ほど登り、さらに下ると、山田池に出ました。
昭和8年に完成した、産業遺産です。

箱木千年家。
呑吐ダムが完成し、移築されてから初めて訪れました。
さわやかな秋晴れの下、いろいろと考えさせられました。
農政についても、十分に対応できておらず、申し訳ありません。
見学の成果を、仕事に生かしていきたいと思います。