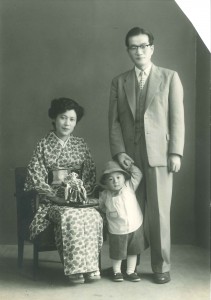1972年春、上京し、小田急線で新宿から2駅目の、参宮橋駅近くにある兵庫県育才会 尚志館 に入寮しました。

東京での生活はスリリングでした。学園紛争は下火になっていましたが、まだ世の中は落ち着いていなくて、大学の授業はなかなか始まらず、新宿駅では争乱も起きていました。
神戸のことは、いつも思い出され、友だちや両親によく手紙を書きました。
確か、入寮した年の秋から、民放のテレビドラマ『日曜日にはバラを』が始まりました。神戸が舞台になっていたので、毎週、欠かさず観ました。
財閥・伊能家の一族をめぐる物語で、伊能家の邸宅は、おそらく、東灘区の岡本か御影のあたりでした。邸宅から臨む神戸の街と海のシーンが、よく映し出されました。
野望を抱く青年(近藤正臣)は、伊能家の当主と令嬢(宇津宮雅代)に取り入り、令嬢と結婚するのですが、青年は妖艶な人妻(鰐淵晴子)と関係を持つことになり、その過程で、伊能家は次第に零落していくことになります。
ラストは、夫である青年を令嬢が刺し殺して終わる、という悲劇的なストーリーで、古典劇のような雰囲気があったのを想い起こします。

40年以上の前のドラマなのですが、いくつかのシーンが蘇ってきました。