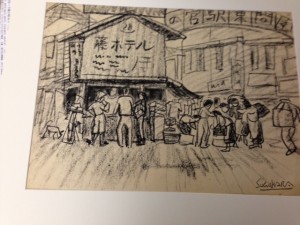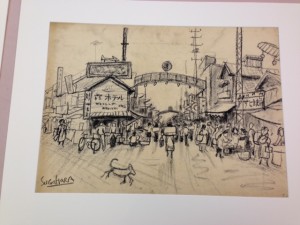平成26年の元旦は、午前2時過ぎから、生田神社、湊川神社、長田神社に、家内とともにお参りしました。
真っ暗でしたが、初詣のみなさんがたくさん来られていました。
それぞれに、子どもの頃から、想い出がある神社です。
心を込めて、参拝させていただきました。
なぜか、心に響いてきたのは、巫女さんが頭上から降り注いでくださった鈴の音です。実に細やかに、幻想的に、響いてきました。
そのとき、なぜかわかりませんが、皇后陛下のお言葉が思い出されました。それは、美智子皇后が、子どもの頃の読書の想い出を語られたときのお言葉です。
美智子皇后は、こう語っておられます。
「読書は、人生の全てが、決して単純でないことを教えてくれました。私たちは、複雑さに耐えて生きていかなければならないということ、人と人との関係においても。国と国との関係においても」
意図せざる鈴の音の、妙なる調べの中に、何か、人を感じさせるところがあったのかもしれません。
そういえば、今年は、午年で、私も、恥ずかしいながら年男です。
世界は、複雑で、不可思議で、奥行きが深く、いつも謎に満ちています。
私は、馬齢を重ねているのに、私たちを取り巻く世界の広さ、深さ、そして、その恐ろしさとともにある魅力について、感じることができてきたのだろうかと、改めて自問自答します。
そのような問いと答えの反復は、今年も繰り返されることでしょう。私は、永遠に、明確な答えを得ることはできないかも知れませんし、ある種の得心も、その対極にある諦念にも、達することができないかもしれません。
そうであったとしても、今年、生きてこの世にあり、自分の周りにある世界を感じ続けていくことができる幸福を、巫女さんが降り注いでくださる鈴の音を聴きながら、感じることができたのでした。
とても、ありがたい年の初めを過ごさせていただくことが出来、感謝しております。