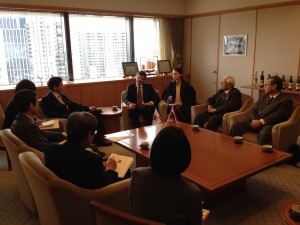きょうは、神戸市・垂水区総合防災訓練が行われました。
訓練に参加いただいた、垂水区の、ふれあいまちづくり協議会、防災福祉コミュニティ、消防団のほか市民のみなさん、警察、自衛隊、地方気象台、国土交通省六甲砂防事務所をはじめ関係機関、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会のみなさん、舞子高校のみなさん、参加各企業のみなさんには、訓練に参加していただき、本当にありがとうございました。
また、危機管理室、消防局など関係職員のみなさんには、ご苦労さまでした。
きょうの訓練では、長く雨が降り続いて地盤がゆるんでいるところに、集中豪雨があり、土砂災害、河川の氾濫が起きたという想定で、救護訓練、避難所開設訓練、複数の救助隊による車からの救出訓練などが行われました。
閉会式の挨拶で、昭和13年の阪神大水害と昭和42年の大水害について触れました。
昭和42年の大水害のとき、私は山田中学校の2年生でしたが、家に帰ろうと、どしゃぶりの雨の中を神戸電鉄湊川駅まで行ったところ、当時、地上駅だった湊川駅は水浸しで、ホームには電車が水没していました。
神戸電鉄、有馬街道は長く不通で、鈴蘭台から市街地へ出るには、西宮の山口まで迂回しなければなりませんでした。
死者・行方不明92人を出した大災害でした。
神戸のように起伏の多い地形に住宅が建てられてきた都市では、ゲリラ豪雨への備えがたいへん重要です。
きょうの訓練結果を検証しながら、地域ぐるみでの防災力を高めていく努力を行っていきたいと思います。