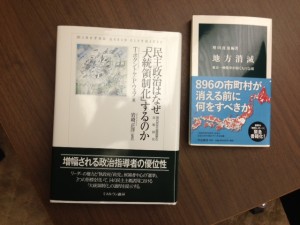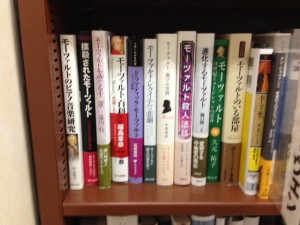前兵庫県知事、貝原俊民さんが、11月13日、神戸市内で交通事故によりお亡くなりになりました。
事故に遭われ、心肺停止、との第一報を受け、ほどなく、ご逝去の知らせが入りました。言葉では言い表せない衝撃でした。
どうしてこんなことになるのか、今でも信じられません。
震災直後の困難な対応、そして「創造的復興」の先頭に立って奮闘された貝原さんを悼む声が広がっています。
私は、1976年に旧自治省に入省して以来、貝原さんには40年近くご指導をいただいてきました。若い頃、県庁に貝原さんをお伺いすると、家族の近況を訊ねて下さいました。
30年前の私ども夫婦の結婚式には、遠いところをご夫妻で出席してくださいました。
貝原さんは、知事を退かれてからも防災や地方自治について積極的に発言され、行動に移されました。10年ほど前、私が総務省で地方自治制度を担当する課長になったとき、貝原さんは、第27次地方制度調査会の委員として参画され、市町村合併、大都市制度、道州制などについて発言されていました。
いつも温かくお声をかけてくださいました。
ちょうど2年前、神戸に戻ってきてからは、私を取り巻く状況がたいへん厳しいことを心配され、いろいろとご助言をくださいました。
震災20年を迎え、行政のトップとして当時どのように対応されたのか、改めて是非お話をお伺いしたい、お聞きしなければいけない、と思っておりましたが、それも叶わぬこととなりました。
最後にお会いしたのは、家内でした。
去る11月9日、丹波の森公苑ホールで開催された「シューベルティアーデ゙たんば」のコンサートで、家内の演奏を聴いて下さり、会場でお声をかけていただき、握手をしてくださったのだそうです。
大きな、厚い手をされていた、と家内から聞いています。