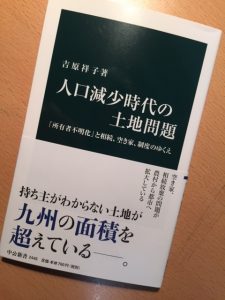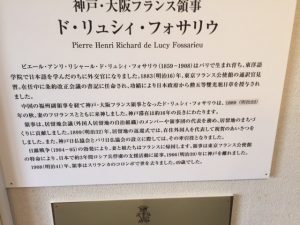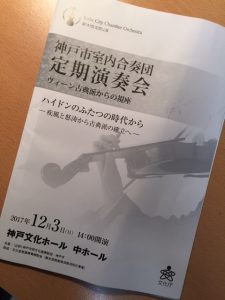今年進化した事業の一つが、東遊園地で土曜日に開催しているファーマーズマーケットではなかったかと思います。
振り返れば、ファーマーズマーケットがスタートしたのは、2015年(平成27年)6月のことでした。
東遊園地を芝生化する社会実験と軌を一にした試みでした。
平成28年度は、ファーマーズマーケットの定期開催と将来的な民間運営のモデルをつくるために、一般社団法人KOBE FARMERS MARKET を設立。
春・夏・秋にそれぞれ10日間の定期開催にチャレンジしました。
今年はお陰様で、年間40回開催することができました。
東遊園地以外の場所での展開を求めて、5月20日、21日には、神戸まつりの時期に合わせて、大丸神戸店の東側道路で開催し、大盛況でした。
このようにファーマーズマーケットが定着したのは、東遊園地の芝生化の実験が成功し、雰囲気が格段に良くなったことも影響していると思います。
市内の至るところで「食」や「農漁業」を発信するイベントが数多く開催されるようになれば、「食都神戸」の本格展開に一歩近づくのではないかと考えます。
2015年6月14日のブログ では、「サンフランシスコの取り組みも参考にしながら、神戸のファーマーズマーケットを進化させていきたいと思います」と記しましたが、たくさんのみなさんの参画と応援のおかげで、確実に進化を遂げていることをありがたく感じています。