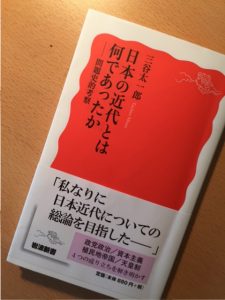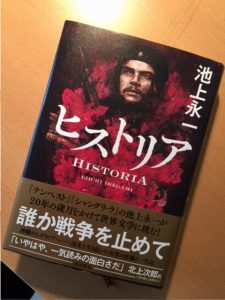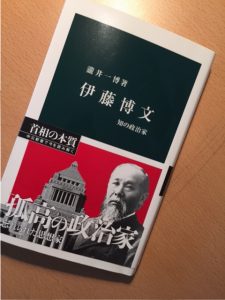
著者は「あとがき」の中でこう記しています。
「歴史好きの人ならば、・・・真っ先に”遊び人”ということが思い浮かぶだろう。確かに彼は醜聞の多い政治家である。”知”ではなく、”痴”だろう、との声が聞こえてくる気がする」
私もそのようなイメージを抱いていた一人でしたが、本書は全く異なる「知の政治家」像を提示します。
伊藤は英語を巧みに操り、津田梅子に対し、「アメリカを知る最良の本」として、トクヴィル『アメリカのデモクラシー』の英訳を渡しています。
愛読していたのでしょう。
若き日から亡くなるまで、伊藤の旺盛な知識欲には目を見張るものがあります。
本書の特徴は、単に伊藤の事績をたどるのではなく、その政治思想を明らかにしようとするところにあります。
有名な「滞欧憲法調査」で、伊藤がグナイストの憲法論を「頗る専制論」と嘆き、「議会政治と行政の調和」を主張するシュタインの国家理論に傾倒するさまが紹介されます。
伊藤は終生、憲法秩序における議会制度を不可欠のものと考え、その漸進的な実現を図ろうとしたのでした。
伊藤が目指した国家像は、「知的水準が高く、権利の保障された人民によって構成される国家」、すなわち「文明国家」でした。
そのために高等教育の発達を期すわけですが、伊藤は、自由民権運動に代表される「政談」や観念的なナショナリズムを嫌い、「利便を生み出し、経済的生活を豊かにする「実学」」の普及を目指したのでした。
伊藤が自ら立憲政友会を結成して政党政治を主導した意図や政治哲学に関する記述も興味深かったです。
丹念に史料を読み込み、「自問自答を重ねて」執筆された本書は、伊藤の思想を提示するのに成功しているように感じました。