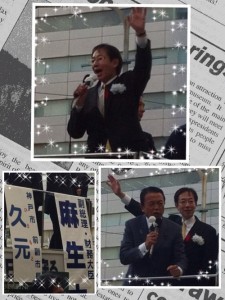明日は、神戸市長選挙の告示。きょうもいろいろなことがありました。
大丸前、三宮センター街での街頭演説。そして、ReKobe 投票率向上プロジェクト 主催の公開討論会・・・・
そんな時間の中で、少年時代の記憶が蘇ってきました。遠い昔の、懐かしく、怖かった光景です。
あれは、確か、鈴蘭台に引っ越したばかりの、昭和39年の秋のことでした。小学校5年生で、神戸電鉄に乗り、湊川の川池小学校に通っていました。
当時、私たち家族は、山を切り開いて造成された小さな団地に住んでいました。
すぐ近くに、団地を見下ろす小高い山があり、その山によく登っていました。弟や友だちと、山の中に秘密の基地をつくったり、カブトムシやクワガタを捕って遊んだものでした。
その山の頂上には、小さな祠があり、祠の横には、大きなアカマツの木がそびえていました。私は、ときどきひとりでこの山の頂上に登って、祠の横に腰を下ろし、自分が住む小さな街を見下ろしたり、空を雲が流れているのを眺めたり、さらに遠くに広がる山々を望んだりするのが好きでした。
ある日、いつものように、祠の横でぼんやりとした時間を過ごしていると、何か不気味な気配がしてきたのです。
祠とアカマツがある、1メートルほど下には、左右に獣道が走り、祠の少し左側で直角に曲がって、麓に下っていました。
不気味な気配は、獣道の右手から漂ってきていました。そして、やがて、何かが、枝や草木を揺らしたり、落ち葉を踏みしめて動いているような音となって近づいてきました。
音が聞こえてくる、獣道の右手の方を見遣ると、それは野犬の群れでした。
野犬の群れが、一列になって近づいて来るのです。
吠えるのでもなく、唸り声を上げるのでもなく、ひたすら、黙々と近づいて来るのです。それが却って恐ろしく、何とも言えない殺気を周囲にまき散らしていました。
もし、見つかったら、かみ殺される、そう思った私は、アカマツの木によじ登ろうとしました。しかし、アカマツには、手の届くところに、登っていけるような枝はありませんでした。
逆方向に逃げると、枯れ草などで音がすることは確実です。ひたすら息を潜め、野犬が通りすぎるのを待つしかありませんでした。
最後の一匹が通り過ぎ、もう戻ってくる気配がなくなるまで、どれだけ長く感じられたことでしょう。
野犬の群れは、10匹どころではなく、20匹以上は確実にいたように思います。ほとんどの野犬が、黒か濃い茶色で、隙間を全くあけることなく、うなり声を上げるでもなく、ひたすら黙々と進んでいくさまは、本当に不気味でした。
助かった、と思って我に返った瞬間、体から力が抜けたように感じたのを覚えています。
私は、長い間、祠の横に寝そべり、雲が流れていくのを見ていました。