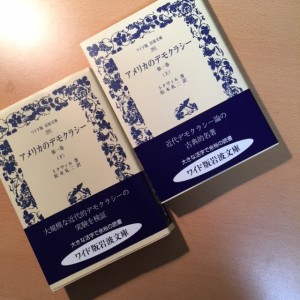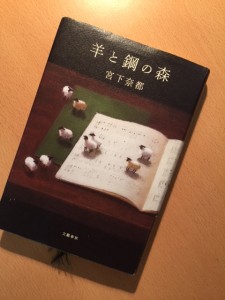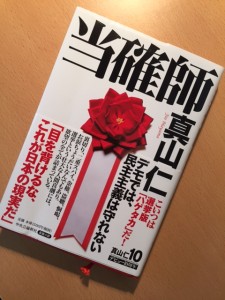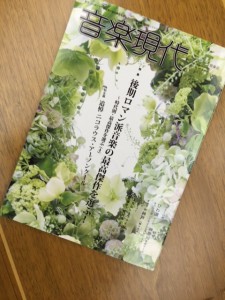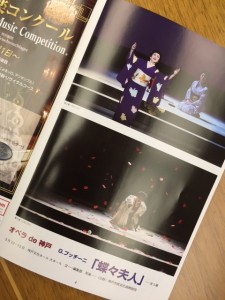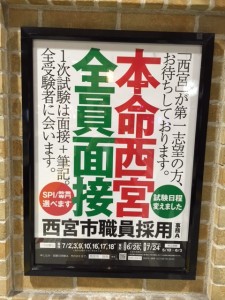東遊園地は、都心の貴重なオープンスペースです。
しかし、中央にあるグラウンドは、行事やイベントの期間以外は、どちらかと言えば閑散としており、さらなる活用が求められていました。

これまで、デザイン都市創造会議などで芝生化の提案がなされ、平成27年9月に策定された「神戸の都心の未来の姿・将来ビジョン」では、たとえば以下のイメージのような、にぎわい創出に向けたエリアと位置付けられました。

これを受け、部分的に芝生化の実験を行ってきましたが、5月31日、いよいよ本格的な芝生化に向けた工事に着工しました。

芝生化した後のエリアでは、追悼式典やルミナリエなどさまざまな行事が行われ、 芝生にも大きな負荷がかかることでしょう。
そこで、芝の種類や保護材、土壌改良材を組み合わせ、10パターン以上の方法を用意し、日常的な利用や大規模イベント時における芝生の損傷具合、その後の回復状況などを検証することにました。
一部の実験区ではビッグロール工法を採用し、工期や養生期間の短縮を目指します。
今回の取り組みがうまくいく保証はなく、あくまでも実験です。
リスクを承知で、さまざまな手法を編み出し、組み合わせながら取り組んでくれている、建設局公園部のみなさんのチャレンジ精神に敬意を表したいと思います。
たくさんの市民のみなさんに参画していただき、東遊園地が、緑あふれる、しっとりとした賑わいのあるエリアに進化していくことができればと念じます。