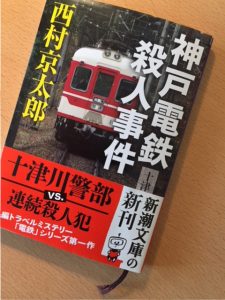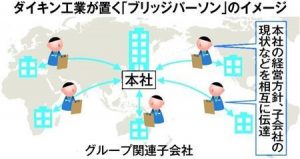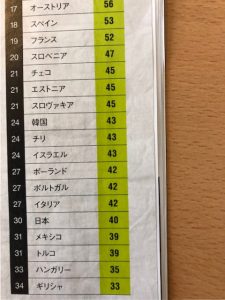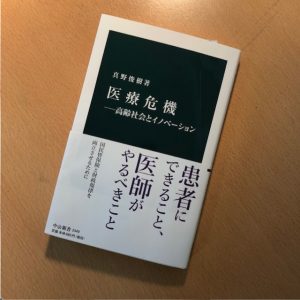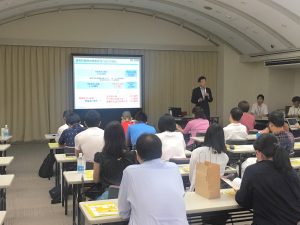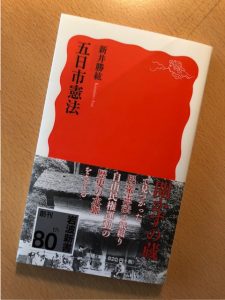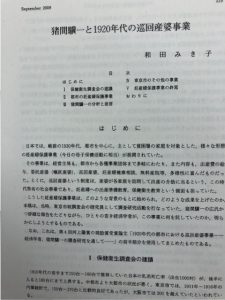
読売新聞(2018年10月3日)朝刊に、「乳児を死なせない 関東大震災後の知られざる奮闘」の見出しで、乳児死亡を減らすために百年前の人々が挑んだ格闘の軌跡が紹介されていました。
著者は、助産師・近代史研究家の 和田みき子 氏です。
和田氏によれば、現在、日本の乳児死亡率(出生1,000あたり)は、2.0程度ですが、100年前、大阪市では200を超えていました。
生まれた子供の5人に1人が、1歳になる前に亡くなっていたのです。
危機感を持ったのは、内務省衛生局でした。
衛生局長を経験し、自身医師でもあった 後藤新平 が内務大臣に就任すると(2018年7月18日のブログ)、1920年、保健衛生調査会から、産院の設置(巡回産婆、産婆養成機関、妊婦相談所の併設)、育児相談所の設置(牛乳供給所の併設)など15項目に及ぶ建議が提出されました。
この中の「巡回産婆事業」を初めて実施したのが、神戸市でした。
詳しく知りたいと思い、保健福祉局を通じて和田氏の論文(上の写真)も入手し、読みました。
同論文によれば、巡回産婆は「出産の際には、連絡があれば、すぐに産家に赴き、分娩一切の処置を行ない、また産後は1週間、産褥婦を回診し、産後処置をするとともに、男児には5日間、女児には6日間・・・沐浴して、乳児哺育の指導を」しました。
また、巡回産婆は、「1週間に一度、月曜日に市役所社会課に出頭して前週の報告をし、衛生材料等の補給を受け」たのだそうです。
全国に先駆けて乳児の命を守るために全力を尽くした先人の努力を思い起こし、その思いを受け継ぎながら、母子の健康を守る取り組みを進めたいと思います。