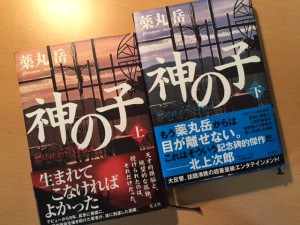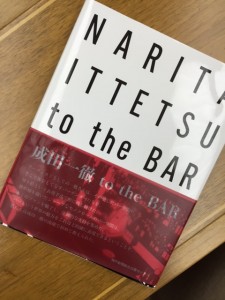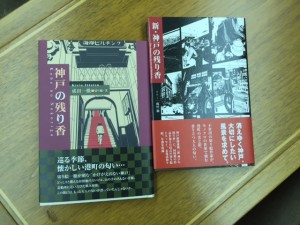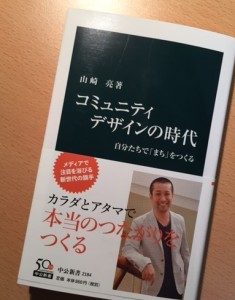いま、東遊園地では、ファーマーズマーケットが開かれています。
是非行きたかったのですが、サンフランシスコに来ていますので、有名なフェリービルディング周辺で行われているファーマーズマーケットにお邪魔しました。
ありとあらゆる食材が売られていて、土曜日ということもあり、物凄い人出です。
CUESAのExecutive Director の Marcy Coburnさんから、マーケットのマネジメントを中心にお話をお伺いすることができました。
もともとは、歴史的建造物であるフェリービルディングの中で行われていたのが、外でも開かれるようになつたようです。
獣肉、魚、蟹、海老、野菜、キノコ、オリーブオイル、チーズなどありとあらゆる食材が売られていて、屋台もたくさん出て大賑わいです。
バッファローの肉まで売られていたのには、驚きました。かなり高価です。
サンフランシスコの取り組みも参考にしながら、神戸のファーマーズマーケットを進化させていきたいと思います。