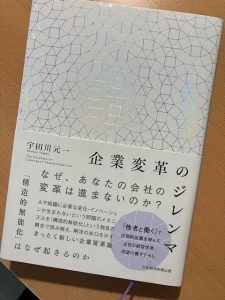
著者は、企業変革の研究・支援を行ってきた経営学者です。
冒頭、「企業変革」とは、「頭脳明晰な経営者が明快な方策を講じ、V字回復を果たす」ことではなく、「経営層、ミドル層、メンバー層によらず、組織に集う一人ひとりが、考え、実行する力を回復する」ことだと説明されます。
「それぞれが、その企業をよりよいものにしていけるという実感を持てるようになること」だと。
ところが、今の日本の企業が陥っている姿は「構造的無能化」です。
「組織の断片化が進む中で思考の幅と質が制約され、それぞれの部門や部署で目先の問題解決を繰り返し、徐々に疲弊して」いるのです。
「構造的無能化」は、次のように生じるとされます。
「分業化とルーティン化」によって「ワイガヤ」などと呼ばれた雰囲気は失われ、組織内の各部門では、全体像が見えない中で割り振られた仕事をこなすだけの「断片化」が進みます。
環境の変化に対する認知の幅が矮小化し、新たな事業の構築や実行が難しくなる「不全化」が進みます。
問題を全体的に捉えることができず、それぞれの部門では、狭い枠組みの中で問題解決を図ろうとする「表層化」が生じます。
どのようにして、現状を変革していくのか。
著者が指摘するのは、「対話」の重要性です。
対話のありようとして、人類学者のフィールドワークが挙げられていることには共感を覚えました。(2022年6月19日のブログ)
対話とは、実際に人と人が話をすることだけではなく、「相手の生きる世界を相手の視点で捉え直し、それに対して自分が応答し、自分が変わっていくプロセスだ」と説かれます。
確かに、「変革」とは、このような地道な取り組みであると感じます。








